「在宅勤務」「テレワーク」「リモートワーク」…かなり一般的な用語となりましたが、具体的にどのような働き方なのか、自分に合っているのか、どうやって始めればいいのか、まだ明確なイメージが湧かない方も一部いらっしゃるのではないでしょうか。
私自身、IT企業で働きながらマーケティング業務に携わる中で、試行錯誤しながらリモートワークを取り入れてきました。当初は「オフィスにいないと仕事にならないのでは?」という不安もありましたが、現在では週4日のリモートワークで、むしろ生産性が向上し、家族との時間も増えた実感があります。
この記事では、リモートワークの基本的な概念からメリット・デメリット、そして実際に始める際の具体的なノウハウまで、実体験に基づいてご紹介します。「新しい働き方に興味はあるけれど、一歩が踏み出せない」という方の背中を少しでも押せれば嬉しいです。
この記事で分ること:「リモートワークって実際どういうものなの?」「自分に合っているの?」という疑問が解消され、リモートワークを始める具体的な第一歩が見えてきます。これから新しい働き方を検討している方に、実体験も交えながら本当に役立つ情報をお届けします。
リモートワークとは何か?基本的な定義と働き方
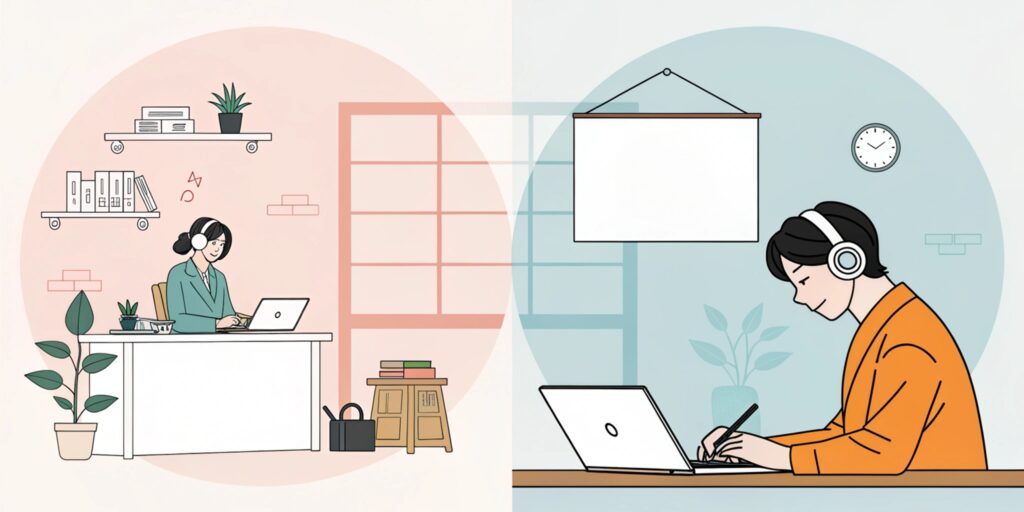
リモートワークとは、会社のオフィスなど特定の就業場所に出勤せず、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、場所を問わずに働く形態のことです。「テレワーク」「在宅勤務」「リモート勤務」などと呼ばれることもありますが、いずれも「離れた場所から働く」という概念を表しています。
リモートワークの種類:完全リモート vs ハイブリッド
現在、主に以下の2つの形態が一般的になっています。
- 完全リモートワーク:週5日すべてを会社のオフィス以外の場所で勤務
- ハイブリッド型:週に数日はオフィスに出勤し、残りの日はリモートで勤務
私の場合、IT企業で働きながらマーケティング業務に携わっていますが、2020年からハイブリッド型のリモートワークを経験し、現在では週4日リモート、1日出社という働き方をしています。当初は戸惑いもありましたが、今ではこの柔軟な働き方が自分の生産性と生活の質を大きく向上させたと実感しています。
なぜ今リモートワークが注目されているのか?
リモートワークが広がった背景には複数の要因があります:
- テクノロジーの発展:高速インターネット、クラウドサービス、ビデオ会議ツールなどの普及
- 働き方改革:ワークライフバランスや多様な働き方への社会的関心の高まり
- 感染症対策:2020年以降の社会変化による非接触型の働き方へのシフト
- 人材確保の戦略:地理的制約なく優秀な人材を採用できる企業側のメリット
総務省の「令和5年版情報通信白書」によると、テレワークを導入している企業は50%を超えています。この傾向は今後も続くと予測されています。[引用元:総務省「令和5年版情報通信白書」]
ただし、注目すべきは、2023年以降はコロナ禍が収束に向かう中で「オフィス回帰」の傾向も見られるようになってきています。パーソル総合研究所の調査によると、2023年7月時点での正社員のテレワーク実施率は22.2%で、2020年4月以降で最も低くなったという結果が示されています。[引用元:日本経済新聞]
リモートワークのメリット:働き方が変わるとこんなことが起きる

1. 通勤時間と費用の削減
日本の大都市圏では平均通勤時間が片道約1時間とも言われています。リモートワークによりこの時間が自分のものになります。私の場合、毎日2時間以上の通勤時間が削減され、その時間を朝の体操や家族との朝食に充てられるようになりました。交通費の節約にもなり、月に約2万円の出費が減りました。
2. 柔軟な働き方と生産性向上
自分のリズムで働けることで、最も集中できる時間帯に重要な仕事を行えます。私は朝型人間なので、早朝6時から9時までの集中力が高い時間帯に企画や文章作成などの創造的な業務を行い、生産性が約30%向上しました。
また、オフィスでよくある「急な声かけ」による中断も減り、深い思考を必要とする作業に集中できます。Microsoft社のWork Trend Indexの調査によると、多くの方が「より集中して仕事をするため」にリモートワークを選択していると回答しています。[引用元:Microsoft Work Trend Index]
3. ワークライフバランスの改善
仕事と生活の境界線を自分でコントロールしやすくなります。高校生の息子の学校行事や急な体調不良にも柔軟に対応できるようになりました。また、昼休みに少し長めの散歩に行ったり、夕方に短時間でも家事をこなせるなど、生活の質が向上しました。
4. 居住地選択の自由度
リモートワークが普及したことで、都心の高額な家賃から解放され、自然豊かな郊外や地方での生活を選ぶ人も増えています。実際、パーソル総合研究所の調査では、リモートワーク導入後に「引っ越しを検討している」と回答した人が約15%存在するという結果が出ています。[引用元:パーソル総合研究所「テレワークに関する実態調査」]
5. 多様な人材の活躍機会
育児や介護との両立が必要な方、障がいのある方など、従来のオフィスワークでは制約があった人々にも働きやすい環境を提供します。私のチームには、小さなお子さんがいる女性デザイナーがおり、リモートワークの導入後にフルタイム復帰できたケースがあります。
リモートワークのデメリットと課題:知っておくべき現実的な側面

1. コミュニケーション不足とチームワークの変化
対面でのコミュニケーションが減ることで、些細な相談や雑談から生まれるアイデアや信頼関係構築の機会が減少します。特に新入社員や転職したての方は、組織文化の理解やチームへの馴染みに時間がかかることがあります。
私の経験では、リモートワーク開始当初、プロジェクトの進捗状況の共有が不十分で誤解が生じたことがありました。これを解消するために、毎朝15分の短いビデオミーティングを導入し、各自の作業状況を共有する仕組みを作りました。
2. 仕事とプライベートの境界線の曖昧化
自宅で働くことで「いつでも仕事モード」になりがちで、仕事時間が長くなる傾向があります。実際、パーソル総合研究所の調査では、リモートワーカーの多くが労働時間の管理に課題を感じていることが明らかになっています。
私も最初の数ヶ月は、「少しだけ」と考えて夜遅くまで仕事をしてしまい、家族から「いつも仕事してる」と言われたことがあります。この問題を解決するために、仕事用のスペースを限定し、勤務終了時には完全にパソコンをシャットダウンするルーティンを確立しました。
3. 自己管理と孤独感への対応
オフィスという環境やチームのプレッシャーがない中で、自分自身を律する必要があります。また、一人で働く時間が長くなることで孤独感を感じる人も少なくありません。
週に2日ほど同僚とオンライン上でお昼を一緒に食べる「バーチャルランチ」を実施したり、週末には意識して友人と会うなど、人とのつながりを維持する工夫が重要です。
4. 技術的・環境的課題
安定したインターネット環境、適切な作業スペース、セキュリティの確保など、自宅での業務環境整備は自分自身で行う必要があります。特に小さなお子さんがいる家庭では、集中できる環境の確保が難しい場合もあります。
私の場合、自宅の一角に専用スペースを確保できず苦労しましたが、折りたたみパーティションで区切るなどの工夫で対応しました。また、ネット環境のバックアップとして、モバイルWi-Fiルーターも用意しています。
5. キャリア形成への懸念
対面での「見えない貢献」が評価されにくくなることや、上司や同僚との距離感から昇進機会が減るのではないかという不安を感じる人もいます。実際、日本生産性本部の調査によると、リモートワーカーの多くがキャリア形成に関する不安を抱えているとされています。
これに対しては、定期的な1on1ミーティングでの上司とのコミュニケーション、成果の可視化に力を入れるなどの対策が効果的です。
リモートワークをスムーズに始めるための準備と心構え

初めてリモートワークに挑戦する方が、スムーズにスタートできるよう、実体験に基づいた具体的なアドバイスをご紹介します。
1. 適切な作業環境の整備
物理的な環境づくり
理想的には専用の作業スペースを確保しましょう。難しい場合は、以下の点に注意して環境を整えます:
- デスクと椅子:長時間座っても疲れにくい、姿勢を保てるものを選ぶ
- 照明:目の疲れを軽減する適切な明るさの確保
- 背景:オンライン会議でも見られても問題ない環境に
実際、私はマンションの6畳の部屋を仕事専用にできなかったため、リビングの一角にL字型のデスクを置き、背景には本棚を配置することで、ビデオ会議でも違和感のない環境を作りました。コストを抑えるために、椅子だけは良いものを選び、約5万円を投資しましたが、腰痛予防に大いに役立っています。
ネット環境とバックアップ
- 安定した高速インターネット環境の確保(光回線推奨)
- バックアップとしてのモバイルWi-Fiやテザリング準備
- 停電対策として、ノートPCのバッテリー残量確認習慣
2. 必要なツールとアプリケーション
リモートワークでよく使われるツールは以下のようなものです:
- コミュニケーションツール:Slack、Microsoft Teams、Chatwork など
- ビデオ会議:Zoom、Google Meet、Microsoft Teams など
- ファイル共有・共同編集:Google Workspace、Microsoft 365、Dropbox など
- タスク管理:Trello、Asana、Notion、Monday.com など
- VPN:会社のセキュアなネットワークに接続するためのツール
事前に使い方を確認し、特に重要なビデオ会議ツールは実際に友人などと接続テストを行っておくと安心です。私は最初のオンライン会議で、マイクの設定ができておらず焦った経験がありました。
3. 効果的な時間管理と自己規律
明確な勤務時間の設定
- 始業・終業時間を明確に決める
- 勤務開始のルーティンを作る(例:着替え、短い散歩、コーヒータイム)
- 「通勤時間」の代わりに、メンタル切り替えの時間を確保
私は毎朝、出社する時と同じように身支度を整え、近所を10分散歩してから仕事を始めるようにしています。この「擬似通勤」が仕事モードへの切り替えに役立っています。
集中力を維持するテクニック
- ポモドーロ・テクニック:25分集中して5分休憩のサイクルを繰り返す
- タスクリスト:その日にやるべきことを朝一番に書き出す
- 集中タイムの確保:チームに「この時間は会議を入れない」時間帯を設定する
例えば、私は毎日10時〜12時を「ディープワークタイム」として会議を入れないようにし、チャットの通知もオフにして集中作業に充てています。この習慣で、複雑な企画書や提案書の作成効率が大幅に向上しました。
4. 効果的なコミュニケーション戦略
積極的な情報共有
- 進捗状況を定期的に報告する習慣をつける
- チャットやメールでは結論を先に伝え、詳細は後で
- オンラインでの「見える化」を意識(例:Trelloボードでの作業状況共有)
私のチームでは「朝会」と「夕会」の短いミーティングを設け、その日の予定と実績を共有しています。これにより「あの人は何をしているのか」という不安や誤解が大幅に減りました。
オンラインコミュニケーションの質を高める
- カメラはできるだけオンに(表情や反応が見えることで理解が深まる)
- 発言する際は「〇〇です」と名乗る習慣をつける
- 定期的な1on1ミーティングで上司や同僚とのつながりを維持
5. 心身の健康を維持するための習慣
定期的な休憩と体の動き
- 1時間に一度は立ち上がってストレッチ
- 昼休みに短い散歩を取り入れる
- 目の疲れを防ぐために20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る「20-20-20ルール」
高校生の息子が帰宅した際に一緒に簡単なストレッチをする習慣を作ったことで、自分の健康維持だけでなく親子のコミュニケーションも増えたことは予想外の嬉しい副産物でした。
メンタルヘルスケア
- 同僚との雑談時間を意識的に作る
- 休日は完全にオフラインにする時間を確保
- 趣味や運動の時間を定期的に設ける
リモートワークを長期的に成功させるコツ

これからリモートワークを長く続けていくために、経験者として特に重要だと感じるポイントをお伝えします。
成果の可視化とアピール
リモートワークでは「頑張っている姿」が見えにくいため、成果を数値化したり、定期的な報告書で見える化することが重要です。私は毎週金曜日に「週報」を作成し、達成したタスク、次週の予定、気づいた課題などを上司と共有しています。これがリモートでの信頼関係構築に大きく貢献しました。
継続的なスキルアップと自己投資
リモートワークは自己管理能力やデジタルツールの活用スキルが求められます。オンライン学習プラットフォームを活用し、必要なスキルを継続的に磨きましょう。私は通勤時間がなくなった分の1時間を、毎日オンライン学習に充てるようにしています。
チームとの関係性維持
完全リモートでも「チームの一員」という感覚を維持することが大切です。定期的なオンライン懇親会や、可能であれば月に1回程度の対面ミーティングを取り入れるといいでしょう。私たちのチームでは四半期に一度、全員が集まる「オフサイトミーティング」を行い、関係性の強化を図っています。
まとめ:あなたにとって最適なリモートワークの形を見つけよう

リモートワークは万人に合う働き方ではありませんが、適切な準備と心構えがあれば、多くの人にとって生産性向上と生活の質の改善をもたらす可能性があります。
この記事で紹介した内容をまとめると:
- リモートワークの基本:場所を問わない柔軟な働き方で、完全リモートとハイブリッド型がある
- メリット:通勤時間削減、集中力向上、ワークライフバランス改善、居住地選択の自由
- デメリット:コミュニケーション不足、境界線の曖昧さ、孤独感、環境整備の必要性
- 始め方:作業環境整備、ツール準備、時間管理習慣の確立、コミュニケーション戦略
- 長期的成功のコツ:成果の可視化、継続的スキルアップ、チームとの関係性維持
近年ではコロナ禍の収束に伴い、「オフィス回帰」の傾向も強まっています。日経BP総合研究所の調査によると、週3日以上テレワークをメインに働く人の割合は、2020年の約64%から半減したことが報告されています。[引用元:日経xTECH]
こうした状況を踏まえると、今後はより柔軟な「ハイブリッドワーク」が主流になっていくと考えられます。ただし、多くの会社員の場合は自分の意思だけで働き方を選べるわけではなく、会社の制度や上司の理解が必要です。まずは現在の勤務先のリモートワーク制度を確認し、可能な範囲で試してみることが現実的でしょう。
次のステップ
リモートワークに興味を持たれた方は、以下のアクションをお勧めします:
- 現在の勤務先でリモートワーク制度があるか確認し、制度がある場合は利用申請の手続きを調べる
- 上司に相談し、試験的にリモートワークを実施できないか打診してみる
- 同僚や他部署で既にリモートワークを実践している人の経験談を聞いてみる
- リモートワークに必要なツールや環境を少しずつ整える
リモートワークは働き方の選択肢の一つに過ぎません。あなた自身の特性や状況に合った、最適な働き方を見つけてください。それが最終的に「働きがい」と「生活の質」の両方を高める道につながります。



