「また SNS で承認欲求を満たそうとしている自分がいる…」
「人からの評価ばかり気にして、自分らしさを失っている気がする…」
「承認欲求が強すぎて、本当にやりたいことができていない…」
このような悩みを抱えていませんか?現代社会では「承認欲求が強い人」「いいねを求める人」などがネガティブに語られることも少なくありません。しかし、心理学的に見ると、承認欲求は人間の基本的な欲求の一つであり、決して「悪いもの」ではないのです。
この記事では、承認欲求の本来の役割や、それを自己成長のバネに変える具体的な方法についてご紹介します。承認欲求と上手に付き合いながら、より自分らしく生きるためのヒントが見つかるでしょう。
この記事でわかること:
・承認欲求は人間の基本的な欲求であり、否定すべきものではないこと
・承認欲求が強くなる心理的メカニズムと、その影響
・承認欲求を自己成長や自己実現につなげる5つの具体的な方法
・健全な承認欲求と不健全な承認欲求の違い
承認欲求とは?その本質と役割を理解しよう

承認欲求とは、簡単に言えば「他者から認められたい」「評価されたい」という欲求です。アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求階層説」では、承認欲求は5段階の欲求のうち4番目に位置づけられています。つまり、人間の基本的な欲求の一つなのです。
マズローの欲求階層説における5つの欲求は以下の通りです:
- 生理的欲求(食べる、眠るなど)
- 安全欲求(身の安全、健康など)
- 所属と愛の欲求(家族や集団への所属感)
- 承認欲求(自尊心、他者からの尊敬)
- 自己実現欲求(自分の可能性を最大限に発揮したい)
出典:マズロー, A.H. (1970). 『人間性の心理学—モチベーションとパーソナリティ』
承認欲求の進化心理学的な意味
人類の進化の過程では、集団から排除されることは生存の危機に直結していました。そのため、「集団から認められる」「仲間から評価される」ことは生き残るための重要な要素だったのです。
ハーバード大学の進化心理学者であるスティーブン・ピンカー博士の研究によれば、人間の社会的行動の多くは集団内での地位確保と密接に関連しており、承認欲求はその原動力となっています。
現代社会における承認欲求の複雑化
SNSの普及により、承認欲求の表出方法や満足させる手段が多様化しました。「いいね」の数や「フォロワー」の数で自分の価値を測ろうとする風潮も生まれています。
多くの研究では、SNSの利用時間と承認欲求の強さには関連性があると指摘されており、特に若年層でその傾向が見られることが知られています。
承認欲求が強くなるメカニズムと影響

なぜ承認欲求が強くなるのか?
承認欲求が特に強くなる背景には、以下のような要因が考えられます:
- 幼少期の経験:無条件の愛情を十分に受けられなかった場合、代償として評価や承認を求める傾向が強まることがあります。
- 自己肯定感の低さ:自分自身を価値ある存在と感じられない場合、外部からの評価に依存しやすくなります。
- 社会的比較の増加:SNSなどで他者の「輝かしい」一面を常に目にすることで、自分も認められたいという欲求が強まります。
心理学者のジェニファー・クロッカー博士らの研究(2003年)では、自己価値を外的な要因(他者の評価や見た目など)に依存させている人ほど、精神的な不安定さを抱えやすいことが示されています。
承認欲求が強い状態の影響
過度に強い承認欲求は、以下のような影響を及ぼす可能性があります:
- 自己決定力の低下:他者の評価を優先するあまり、本当にやりたいことや自分らしさを見失う
- メンタルヘルスの悪化:常に他者の評価を気にすることでストレスや不安が増大
- 人間関係の質の低下:承認を得るための行動が増え、真の交流が減少
- 自己成長の機会の損失:失敗を恐れて新しいことに挑戦できなくなる
心理学の研究では、承認欲求が強すぎる人は、批判や否定的なフィードバックに過剰に反応し、長期的な目標達成が困難になる傾向があることが指摘されています。
承認欲求は悪いものではない—ポジティブな側面

承認欲求にはネガティブな側面だけでなく、ポジティブな側面も多くあります:
1. モチベーションの源泉になる
承認欲求は、私たちを行動に駆り立てる強力な動機づけになります。「認められたい」という気持ちが、努力や成長を促進することは多くの研究で示されています。
スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授の「マインドセット理論」によれば、承認欲求が「成長マインドセット」(能力は努力で伸びるという考え方)と結びつくとき、大きな成長の原動力になると説明されています。
出典:Dweck, C.S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
2. コミュニケーション能力の向上
他者から認められたいという欲求は、相手の気持ちや状況を理解しようとする共感能力や、自分の考えを適切に伝える表現力の向上につながります。
3. 社会的絆の強化
適度な承認欲求は、人間関係の構築・維持に重要な役割を果たします。互いを認め合う関係は、信頼関係の構築や協力行動の促進につながります。
4. 自己理解の深化
「なぜ認められたいのか」を探ることで、自分の価値観や信念を明確にし、より深い自己理解につながることがあります。
健全な承認欲求と不健全な承認欲求の違い

承認欲求自体は自然なものですが、その表れ方や影響には健全なものと不健全なものがあります。
健全な承認欲求の特徴
- 内発的動機と結びついている:「認められたい」という気持ちが、自分自身の成長や価値観の実現につながっている
- 多様な価値源を持つ:承認を得る対象や場面が多様で、一つの評価に依存していない
- 長期的な視点がある:目先の評価だけでなく、長期的な成長や貢献を意識している
- 他者との協力や共感を促進する:一方的に評価を求めるのではなく、互いに高め合う関係性を築ける
不健全な承認欲求の特徴
- 外発的動機に偏っている:自分の価値観よりも外部からの評価を優先する
- 特定の評価に依存している:「いいね」の数や特定の人からの評価に過度に依存する
- 短期的な満足を求める:長期的な成長よりも、即時的な評価や称賛を求める
- 他者との競争や比較を促進する:他者を下げることで自分の価値を高めようとする
臨床心理士の松岡洋一氏は「承認欲求そのものではなく、その満たし方が問題になる」と指摘しています。
承認欲求を自己成長のバネにする5つの方法
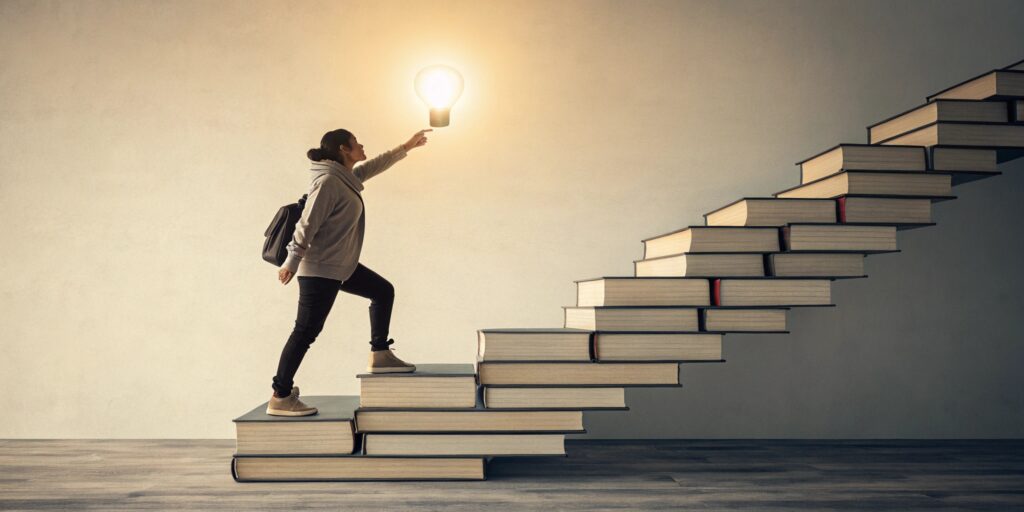
承認欲求を否定するのではなく、それを活かして自己成長につなげる具体的な方法を紹介します。
1. 承認欲求を「知る」:自己観察を深める
まずは自分の承認欲求のパターンを観察しましょう。以下のような質問を自分に投げかけてみてください:
- どんな場面で特に認められたいと感じるか?
- その欲求の背景には、どんな価値観や信念があるか?
- 承認が得られないとき、どんな感情や反応が生まれるか?
心理学者のリチャード・ライアン博士とエドワード・デシ博士が提唱する「自己決定理論」では、自己の行動や感情を意識的に観察することが、自律性の向上につながると説明されています。
2. 承認の「源泉」を多様化する
承認を得る対象や場面を意識的に多様化することで、特定の評価への依存度を下げることができます。
- 仕事だけでなく、趣味やボランティア活動など異なる場での承認体験を増やす
- 特定の人からの評価だけでなく、様々な人間関係の中で承認を受ける経験を重ねる
- 「結果」だけでなく「プロセス」や「努力」に対する自己承認を意識する
心理学の研究によれば、複数の領域で承認経験を持つ人ほど、精神的レジリエンス(回復力)が高い傾向にあることが知られています。
3. 「自己承認」の習慣を育てる
他者からの承認だけでなく、自分自身が自分を認め、価値を見出す習慣を育てることが重要です。
- 日々の小さな成功や成長を意識的に認識し、自分を労う習慣をつける
- 自分の強みや unique な特性を言語化し、意識する
- 完璧主義から脱却し、「十分にいい(good enough)」という感覚を育てる
心理学者のクリスティン・ネフ博士が提唱する「セルフ・コンパッション」の考え方では、自分自身に対する思いやりと理解が、健全な自己評価の基盤になると説明されています。
4. 「貢献」の視点を取り入れる
承認を「得る」ことだけでなく、他者や社会に「与える」視点を取り入れることで、承認欲求の質が変化します。
- 自分のスキルや知識で誰かの役に立つ機会を意識的に作る
- コミュニティへの貢献や社会的意義のある活動に参加する
- 他者の成長や成功を支援する経験を増やす
ハーバード大学の心理学者マーティン・セリグマン博士の研究によれば、「意味のある貢献」の実感は、持続的な幸福感と強い相関があることが示されています。
5. 「成長志向」の承認欲求に転換する
承認欲求を「証明型」から「成長型」へと質的に転換することで、持続的な自己成長につながります。
- 「失敗しないこと」より「挑戦すること」に価値を置く
- 「今の能力を示す」より「新しいスキルを習得する」ことを優先する
- 「他者との比較」より「過去の自分との比較」に焦点を当てる
スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授の研究によれば、「成長マインドセット」を持つ人は、困難に直面しても粘り強く取り組み、長期的に大きな成長を遂げる傾向があるとされています。
承認欲求と上手に付き合うための日常的な実践法

マインドフルネスの実践
瞬間瞬間の自分の感情や思考に気づき、それに巻き込まれすぎないよう意識することで、承認欲求に振り回されにくくなります。
複数の研究では、マインドフルネスの継続的な実践が、自己評価の安定性と外的評価への依存度低下に効果があることが示されています。
「価値観の明確化」ワーク
自分にとって本当に大切なものは何かを明確にすることで、承認欲求を自分の価値観と整合させやすくなります。
アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)の創始者であるスティーブン・ヘイズ博士は、「価値に基づいた行動」が心理的柔軟性を高め、外的評価への依存を減らすと説明しています。
「共感と感謝」の習慣化
他者の貢献や存在を認め、感謝を表現する習慣をつけることで、承認のギブ&テイクのバランスが整います。
エモンズ博士らの研究によれば、感謝の習慣化は自己価値感の安定につながり、外的評価への依存度を下げる効果があるとされています。
承認欲求を味方につける—まとめ

承認欲求は、決して否定したり、排除したりすべきものではありません。それは人間として自然な欲求であり、適切に活用すれば、自己成長や人間関係の充実、社会貢献などにつながる大切なエネルギーになります。
この記事でご紹介した5つの方法を実践することで、承認欲求を「振り回される対象」から「自己成長のバネ」へと転換することができるでしょう:
- 承認欲求を「知る」:自己観察を深める
- 承認の「源泉」を多様化する
- 「自己承認」の習慣を育てる
- 「貢献」の視点を取り入れる
- 「成長志向」の承認欲求に転換する
心理学者のアルフレッド・アドラーは「承認欲求は、共同体感覚と結びつくとき、最も建設的な形で表現される」と述べています。つまり、承認欲求を「個人の優越性」ではなく「相互の成長や貢献」につなげるとき、それは私たちの人生を豊かにする力になるのです。
あなたの承認欲求も、決して「悪いもの」ではありません。それを理解し、味方につけることで、より自分らしく、充実した人生を築いていきましょう。








